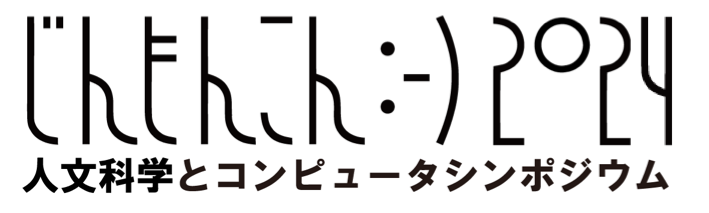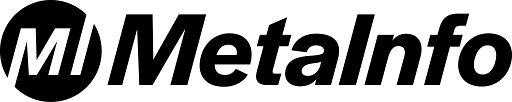じんもんこん2024は終了しました。たくさんの方々のご来場ありがとうございました。
審査員による投票の結果、各賞は、以下の発表に決定いたしました。おめでとうございます。
じんもんこん2024優秀論文賞
A-3-3:荘園関係データベースを活用した「nihuBridge LOD」の構築と学校教育への応用
大井 将生;中村 覚;大野 健人;髙橋 傑
P-1-7:CPU環境で高速に動作する軽量OCR「NDL古典籍OCR-Lite」の開発
青池 亨
じんもんこん2024ベストポスター賞
P-2-5:TEIによる編纂史料の構造化ー『大日本史料』を例に
小風綾乃; 中村覚; 山田太造
P-2-8:コンテクスト指向翻訳による古典テキスト意味検索精度の向上
岩田直也;田中一孝;小川潤
じんもんこん2024学生奨励賞
A-2-2:小袖資料の3D鑑賞と仮想試着を目的とした博物館展示デザイン
中池天音;曽我麻佐子;澤田和人;後藤真
P-2-6:国会会議録を用いたESG関連テーマの抽出とその変容に関する分析
牛尾 久美; 大向 一輝
P-2-7:国語教科書助動詞分類データベースの構築
久保柾子;小木曽智信
P-2-15:画像とメタデータの視覚化による歴史資料探索支援システムの提案
田中駿平;奥野拓
趣旨
「デジタルアーカイブ」は、これまでの人文科学とコンピュータ研究会の中で、そしてデジタルヒューマニティーズ全体の議論の中でも焦点が当たり続けてきたトピックであるが、2020年に日本のデジタルアーカイブを横断検索出来る「ジャパンサーチ」が公開されることで、改めて注目を浴びるようになった。2022年には国立国会図書館デジタルコレクションが大幅に更新されて話題を呼んだが、同年には博物館法の改正も行われ、そこでは資料のデジタルアーカイブ化が博物館事業の一つとして新たに明記された。さらに同年には公文書管理法施行令・ガイドラインの改正が行われ、国の公文書は電子文書での管理を基本とすることが明記された。日本の公共機関が運営するデジタルアーカイブには現在大きな期待が寄せられている。
そこで本シンポジウムでは、所有する学術・文化資源を横断的に検索出来る「東北大学総合知デジタルアーカイブ」を2024年に公開した東北大学を会場として、デジタルアーカイブを中核に据えたMLA(博物館・図書館・文書館)連携をテーマに設定したい。デジタルアーカイブをMLA各機関の紐帯として考えてみると、それぞれの特長はどのように活かされ、何が期待出来るのか、現状の課題や今後の見通しについての闊達な議論が展開されることを望む。
開催概要
日程
2024年12月7日(土)〜8日(日)
会場
東北大学 川内キャンパス 文科系総合講義棟(会場A・B)・附属図書館本館(会場P)

(クリックするとGoogle Mapに飛びます、周辺ランチマップはこちら)
※昼食はキャンパス施設を利用できず、また近くで購入も出来ないので、各自電車を使って仙台駅近くまで移動してください。(昼休憩に100分以上取っております。)
共催
東北大学統合日本学センター
東北大学総合知デジタルアーカイブ運営委員会
東北大学学術資源研究公開センター
東北大学附属図書館
後援
実行委員会
加藤諭(東北大学)【委員長】
鈴木親彦(群馬県立女子大学)、小川潤(人文学オープンデータ共同利用センター/東京大学)、橋本雄太(国立歴史民俗博物館)、耒代誠仁(桜美林大学)、田村光平(東北大学)、岡安儀之(東北大学)、片倉峻平(東北大学)
プログラム委員会
堤智昭(筑波大学)【委員長】
大向一輝(東京大学)、亀田尭宙(人間文化研究機構)、北本朝展(国立情報学研究所)、吉賀夏子(大阪大学)、鹿内菜穂(亜細亜大学)、高田智和(国立国語研究所)、李媛(京都大学)、上阪彩香(大阪成蹊大学)、松村敦(筑波大学)
主なトピック
人文科学とコンピュータ研究会の理念に即したテーマについての研究発表・事例報告などについて広く歓迎いたします。具体的なトピックは以下に挙げますが、この限りではありません: デジタル・アーカイブ(記録、保存もしくは活用に関する技術、事例、理論など)、保存科学、文化財防災、MLA連携、デジタル博物館、デジタル化文書、ドキュメンテーション、考古学・歴史学・文献学・言語学などの人文系諸学を含むデジタル・ヒューマニティーズ、人文情報学、時空間情報、視覚化、データ・マイニング、色彩情報処理、情報技術を用いた教育、WEB活用、情報検索、メタデータ、知的財産権・著作権課題など、広く 人文科学とコンピュータ研究会の理念に即したテーマ、事例、現状批判、問題提起などについてのご発表も広く歓迎いたします。
発表論文募集
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 募集開始 | |
| 概要論文締切 |
|
| 論文採否通知 | |
| カメラレディ論文締切 |
概要論文の応募について
-
A4判2ページ(図表を含む)の概要論文を作成してください。
査読方針、概要論文の書き方、送付方法などについては、 以下のフォーマットに詳しい情報がありますので、 ダウンロードの上、必ず参照してください。 -
2024年度、
じんもんこんシンポジウムはシングルブラインド制を採用します。 著者・所属も概要論文に記載をお願いします。 -
概要論文には希望する発表形式(口頭、ポスター、デモ、
どちらでもよい)を明記してください。 -
原則として筆頭著者および発表者となれるのは、
企画セッションを除いて著者一人につき1発表とします。 共著者には特に制限はありません。 -
学生が第1著者の場合は、学生奨励賞の審査対象となりますので、
審査希望の有無を選択してください。 -
提出された概要論文に基づいて、プログラム委員会で査読・
審査の上、応募論文の採否を決定します。 -
採択された場合、
A4判6ページか8ページの論文集用カメラレディ論文を提出して
いただきます。
概要論文の投稿について
- じんもんこん2024では、概要論文の投稿にオンライン投稿システムEasyChairを利用します。EasyChairのアカウントをすでにお持ちの方は、そのアカウントを利用してログインしてください。アカウントをお持ちでない方は、新規にアカウントを作成してください。
- じんもんこん2024 EasyChairページ よりログインし、概要論文を提出してください。
- 投稿ファイルのファイル形式はPDFのみとします。
- 投稿時、「著者情報」「タイトル」「キーワード(3語以上)」「希望発表形式」を入力して、申し込みをしてください。 ※「著者情報」「タイトル」は、概要論文が和文の場合は日本語で、英文の場合は英語で入力してください。 ※「キーワード」は、日本語入力するとエラーが出る事例が報告されているため、概要論文が和文・英文にかかわらず、英語で入力してください。
- 投稿後、すぐにEasyChairから確認メール(受理通知)が送付されます。確認メールが届かない場合は、お問い合わせください。 ※EasyChairから確認メール(受理通知)が届かない場合は、投稿が正常に完了していません。
- 概要論文締切までの期間であれば、何度でも概要論文のアップデートが可能です。
- EasyChairの詳細な操作方法はEasyChairの使い方をご覧ください。
- 概要論文作成、投稿に関して不明な点があれば、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
発表形式
- いずれのセッションも対面発表です。オンライン配信は行いません。
口頭発表
- 1発表につき発表25分(ただし、前の人との入れ替えを含む)と質疑5分の合計30分となります。
ポスター発表
- 原則として、じんもんこん2024の開催期間中、指定の場所にポスターを掲示します。
- ポスター・デモセッション(コアタイム)で、1発表につき1分間のライトニングトーク(ポスター・デモ紹介)を行います。
- ポスター・デモセッション(コアタイム)で、質疑応答を行います。
デモ発表
- 原則として、じんもんこん2024の開催期間中、指定の場所にポスターを掲示します。
- ポスター・デモセッション(コアタイム)で、1発表につき1分間のライトニングトーク(ポスター・デモ紹介)を行います。
- ポスター・デモセッション(コアタイム)で、デモと質疑応答を行います。
アクセス情報
最寄駅:川内駅[南2出口](仙台市地下鉄東西線)
駅から会場まで徒歩で5分ほどかかります。
※昼食はキャンパス施設を利用できず、また近くで購入も出来ないので、各自電車を使って仙台駅近くまで移動してください。(昼休憩に100分以上取っております。)
参加申込
申込方法
早期申込み割引は11/22(金)までです!
情報処理学会の 申し込みフォーム からのお申込みになります。参加費についてはそちらでご覧ください。なお、本シンポジウムでは、各発表に対して1名以上の有償での参加登録をお願いしております。
※学生(論文集なし)の方は
専用のフォーム
より参加登録ください。
懇親会 ※受付は終了しました。
懇親会参加費:一般6000円・学生2000円
申込締切:11/25(月)
懇親会参加をご希望の方は、シンポジウム参加申込時にオプションで懇親会をご選択ください。マイページへ請求書を発行させていただきます。
※シンポジウムの参加費と懇親会費の請求書は分けることは出来ませんのでご了承ください。
(領収書は明細毎に分けて発行可能です。)
※シンポジウム参加費とは別です。
懇親会会場:東北大学川内南キャンパス 文系食堂(文科系厚生施設(メイプルパーク川内)内)
※当日受付は致しません。必ず締切までに受付をお済ませください。
問い合わせ
jmc2024■googlegroups.com(■を@に変えてください)